フルカウルバイク、前傾ヤバさランキング【国内全30車種】
2024.02.25

バイクや車を購入する際、見積書によく記載されている「登録代行費用」。本来、登録手続きは購入者自身が行うこともできるのですが、販売店によっては「代行を断るなら販売できない」と言われるケースもあります。
例えば、あるバイクショップで400万円近い大型バイクを購入しようとした人が、「登録は自分でやります」と申し出たところ、「それはできません」と断られてしまいました。理由を尋ねると、「会社の方針で、代行を拒否する客は追い返すように言われている」とのこと。
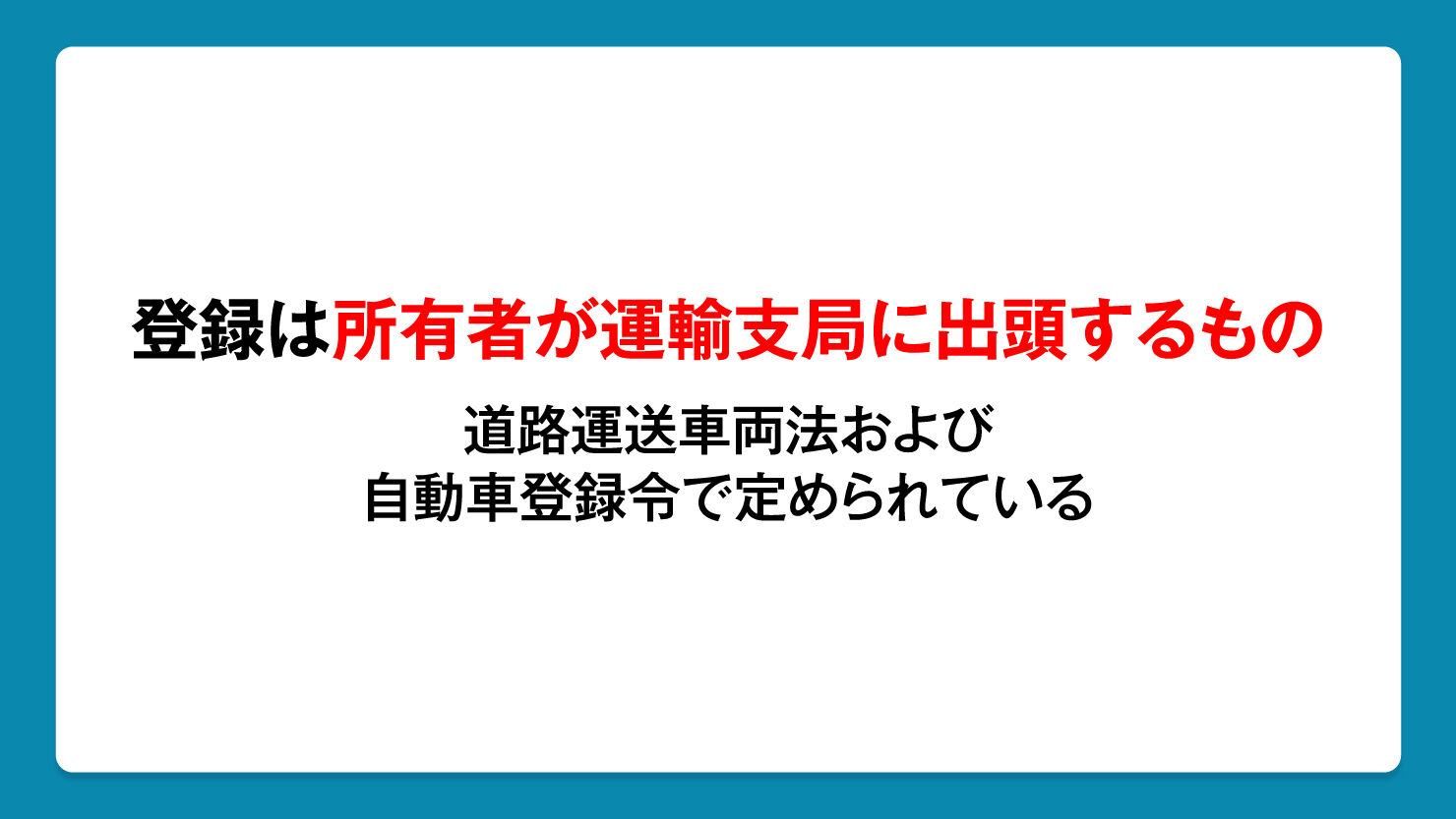
登録は所有者が運輸支局に出頭するものと道路運送車両法および自動車登録令で定められている
インターネットを使えば、登録代行を1万円程度で請け負う業者も見つかります。それなのに、なぜ店舗で高額な代行費用が当然のように請求されるのでしょうか?
本記事では、「登録代行費用」の仕組みや相場、自分で登録する際の手順について、わかりやすく解説していきます。※この物語は実話を基にしたフィクションです。
ある購入希望者が、ヤマダドリームジャパンが運営する販売店を訪れた際のことです。見積書には「登録代行費用」として3万3,000円が記載されており、本人が「登録は自分で行いたい」と申し出たところ、販売店からは「できない」と一蹴されました。
理由としては、「会社の方針で登録は必ず代行」「代行を断るなら契約できない」といったもの。さらに、「完成検査証を紛失すると面倒だから」という事情も挙げられました。
しかし、2025年4月以降、二輪の新車登録はオンライン(OSS)化され、完成検査証は電子化が前提となっています。紙の紛失リスクを理由とする制限は、時代遅れともいえる状況です。
一方で、スズキワールドやカワサキプラザといった他メーカーの直営店では、登録代行はあくまで任意であり、購入者が自ら手続きを行うことも問題なく認められています。同じような企業構造にもかかわらず、対応に差があるのは注目すべき点です。
また、3万円を超える代行費用について「行政書士に委託しているため」と説明されましたが、実際にはバイク登録でこれほどの費用を請求する行政書士は稀です。法的には、有償での申請代行は行政書士に限られますが、費用の妥当性には疑問が残ります。
こうした販売店の対応は、登録を希望する消費者の選択肢を狭めるものです。次章では、登録手続きを自分で行う方法や、費用を抑える現実的な選択肢について解説します。
販売店の返答を待つ間に、バイクの登録手続きについて確認しておきましょう。登録方法には主に2通りあり、オンライン申請(OSS:ワンストップサービス)と、従来の紙申請があります。

引用:https://www.oss-webupload.mlit.go.jp/
OSSは、2025年現在、二輪の新車新規登録にのみ対応しています。国土交通省のOSSポータルサイトにアクセスし、マイナンバーカード(個人)または電子証明書(法人)を用いて申請を行います。
画面に沿って情報を入力していけば登録申請は完了します。入力項目は多めですが、手続き自体はそれほど難しくありません。ただし、オンラインで手続きが完了しても、平日に運輸支局へ出向いて車検証とナンバープレートを受け取る必要があります。郵送対応はありません。
この運輸支局での受け取りについては、OSSであっても紙申請であっても同様で、窓口で番号札を取り、順番を待つ必要があります。受付時間は通常、平日の16時までに限られるため、日中に時間を確保できない人にとってはややハードルが高いでしょう。
紙申請では、OSSでのデータ入力の代わりに、運輸支局の窓口でOCR用紙などの専用書類に記入します。申請内容や訪問の手間を考えると、OSSと紙申請の違いはそこまで大きくなく、どちらを選んでも窓口訪問は避けられません。
平日に窓口へ行くのが難しい場合は、代行サービスの利用も現実的な選択肢です。販売店が提供する代行は3万円以上かかることもありますが、一般的なオンライン代行サービスなら1万円前後で依頼可能で、カード決済にも対応しています。

引用:https://kantancar.com/
手続きの流れもシンプルで、Web上で必要情報を入力し、指定の書類を郵送するだけ。登録が完了すれば、車検証とナンバープレートは自宅に郵送されるため、運輸支局へ出向く必要はありません。
なお、地域の行政書士に直接依頼すれば、さらに安く済む可能性もありますが、初めての個人客には現金先払いなどの条件が課されることもあり、ややハードルが高めです。その点、全国向けの代行サービスなら、安心して使える仕組みが整っているため、初めてでも利用しやすいでしょう。
バイクの登録手続きを語るうえで欠かせないのが、OSS(ワンストップサービス)です。これは、車両の登録手続きをオンラインで行える仕組みで、もともとは普通車向けに提供されていたものですが、2025年4月からは二輪の新車新規登録にも対応するようになりました。
一方で、中古車や名義変更などは引き続き紙申請に限定されており、すべての手続きが完全にオンライン化されたわけではありません。
二輪の新車登録には、完成検査証(=車両の合格証明書)の提出が必要です。従来の紙申請では、この完成検査証も紙で受け取り、保管したうえで運輸支局に提出する必要がありました。
ところが、紙を紛失してしまうと再発行に数ヶ月かかるケースもあり、登録そのものが長期間できなくなるというリスクがありました。
OSSでは、この完成検査証が電子化され、メーカーからサーバー上に直接登録される仕組みになっています。そのため、申請者が紙の書類を紛失する心配がなくなり、大きな安心材料となっています。
かつて「完成検査証の紛失リスクがあるから登録は代行させてほしい」とされていた理由も、OSS導入によってほぼ意味を失ったと言えるでしょう。
では、OSSを使えばすべてが便利になるのかというと、そう単純でもありません。申請の手順そのものはオンライン化されたものの、車検証とナンバープレートは依然として運輸支局で直接受け取る必要があります。
つまり、紙申請と同様に平日に窓口に出向き、番号札を取って待つという流れに変わりはありません。入力が手書きかパソコンかの違いこそあれ、現場での手続き負担は大きくは減らないのが現状です。
バイク購入時の「登録代行費用」には、実は法律上の制約が関係しています。この章では、行政書士法と個人情報保護法という2つの法律の観点から、登録代行の問題点を見ていきます。
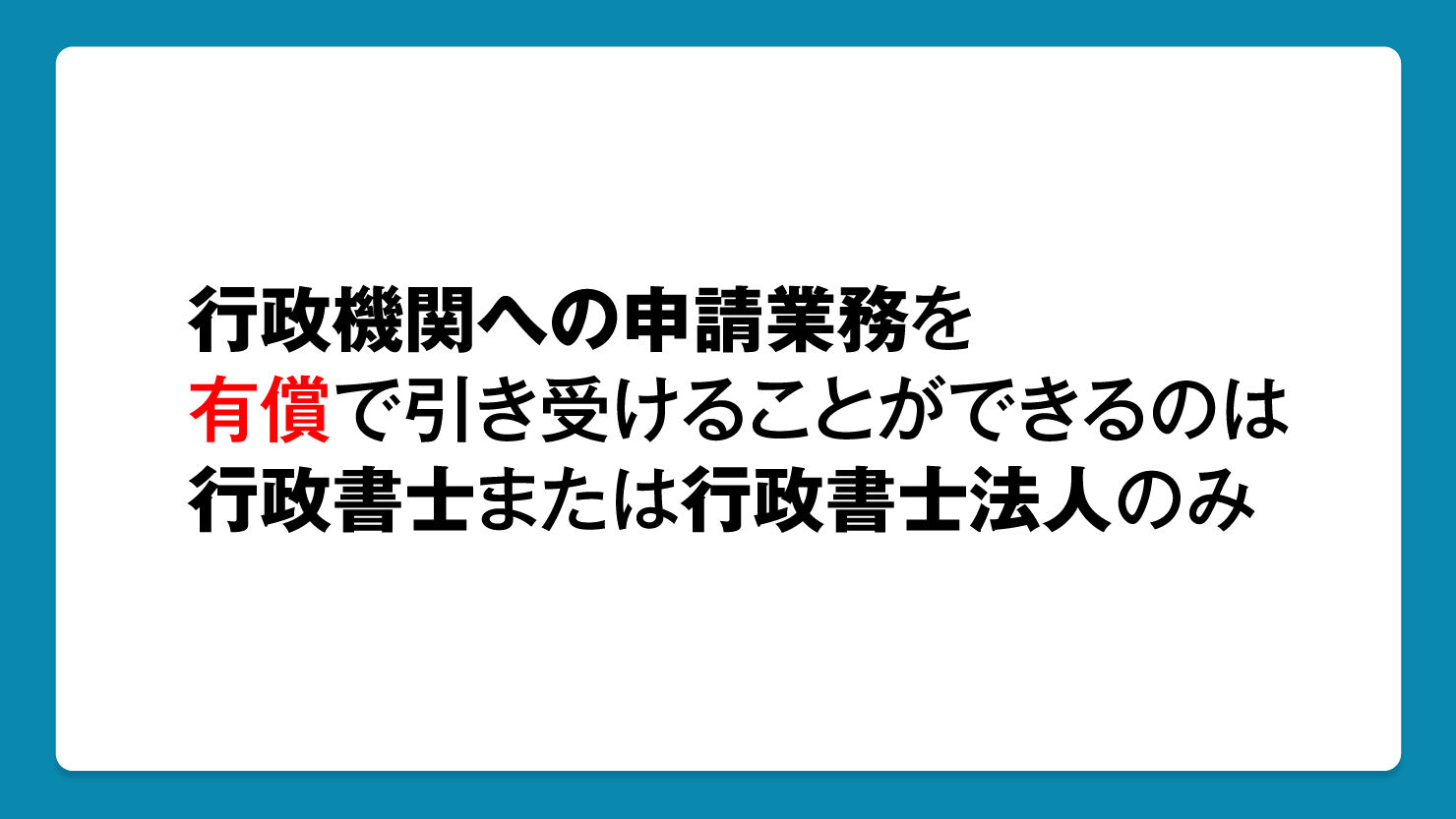
行政機関への申請業務を有償で引き受けることができるのは行政書士または行政書士法人のみ
行政書士法:有償代行は行政書士に限られる。
まず、行政書士法では、行政機関に提出する書類の作成や申請代行を有償で行うことができるのは、行政書士または行政書士法人に限ると明確に定められています。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
無償で行うのであれば問題ありませんが、報酬が発生する場合は明確に違法となります。
販売店が「登録代行費用」として3万円超を請求している場合、その業務が行政書士を通さずに行われているのであれば、行政書士法違反の可能性があります。仮に行政書士に委託していたとしても、その費用としては相場を大きく上回っており、不透明な点が残ります。
登録代行の強制と個人情報保護法。
さらに問題となるのが、個人情報保護法の観点です。登録代行を行う場合、ユーザーは住民票や印鑑証明書などの個人情報を第三者に渡すことになります。この情報提供は、本人の明確な同意があって初めて合法となります。
ところが、「代行を断るなら販売しない」という姿勢をとる店舗では、ユーザーが同意を強制されているような状況が発生します。これは実質的に情報提供を強要していることになり、法的に非常に問題のある行為です。
メーカー側の見解。
主要バイクメーカー各社は、いずれも「登録代行を強制することは望ましくない」という姿勢を示しています。ただし、販売は別会社に委託している場合が多く、「販売会社の運用には関知しない」として責任を明確にしないケースも見られます。
ヤマダドリームジャパンの登録代行費用について、後日改めて確認を行ったところ、社内で一定の議論と方針整理が行われていたことがわかりました。
担当者の話によると、販売店内部でも「登録代行の強制は問題がある」との意見が多く、法的観点から見ても購入者の主張が正当であることは認識されていたとのことです。
ただし、全国に複数の店舗を展開していることもあり、社内の調整には時間がかかったようです。
最終的には次のような対応方針が打ち出されました:、・250ccを超える新車については、購入者が自分で登録手続きを行っても問題なし、・250cc以下の車両および中古車については、これまで通り販売店側での代行を希望。
この対応は、完全な自由化とは言えないものの、従来の「すべて強制代行」からは明らかに改善された方針です。
背景には、「これまで登録代行を一律で強制してきた経緯との整合性を保ちたい」という販売側の事情もあるようです。特に、2025年4月以降、新車登録では完成検査証が電子化され、紛失リスクがなくなったことにより、登録代行を強制する理由がさらに薄れています。
もしもこのまま代行を強制し続ければ、法的な根拠もなく、高額な費用を請求していることになりかねないため、販売店としても慎重な姿勢に転じたものと思われます。
バイク購入時の登録手続きについて、ここまでさまざまな角度から見てきました。最後に、要点を簡潔に整理します。
現在、登録代行の強制は法的にも制度的にも認められていません。販売店で「登録は自分で行いたい」と伝えることはまったく問題なく、正当な主張です。
特に新車(250cc超)の場合は、OSS(オンライン申請)を利用すれば、必要事項を入力し、車検証とナンバープレートを平日運輸支局で受け取るだけで完了します。
平日の昼間に時間が取れない人や、手続きに不安がある人は、1万円前後で利用できるオンライン代行サービスがおすすめです。Web上で申し込み、必要書類を送れば、車検証とナンバープレートは自宅に郵送され、運輸支局に出向く必要はありません。
また、行政書士に直接依頼することも可能ですが、費用の支払い方法ややり取りがやや煩雑な場合もあります。全国対応の代行サービスの方が安心して使えるケースが多いでしょう。
販売店によって、登録手続きの扱いには違いがあります。代表的な例は以下のとおりです:、・スズキワールドは強制なし。自分での登録を受け入れてくれる。・ヤマダドリームジャパンは一部緩和(新車は任意) 。250cc超の新車は自分で登録可能。中古車と250cc以下は要相談。・カワサキプラザ(FC中心) 基本的に強制なしだが店舗により異なる。フランチャイズなので対応差あり。・YSP(ヤマハ)はフランチャイズごとに異なる。店舗ごとの交渉が必要。
このように、販売店の方針は全国一律ではなく、交渉や確認が必要なケースも多いのが実情です。
OSSの導入により、完成検査証の電子化が進み、書類紛失リスクという代行強制の根拠も失われました。にもかかわらず代行を強制し、高額な手数料を請求するような行為は、法的にもモラル的にも許されるものではありません。
個人情報保護法では、本人の同意なき個人情報提供はNG。
こうした法令を無視する販売手法に対しては、消費者側が正しい知識を持ち、毅然と対応することが重要です。
バイクの登録手続きは、本来、購入者自身が行うことも可能であり、必ずしも販売店に任せなければならないものではありません。2025年からのOSS導入により、新車登録に関しては書類紛失のリスクも解消され、代行を利用する必要性は以前よりも低くなっています。
それでも一部の販売店では、高額な代行費用が提示されることがあり、背景には行政書士法や個人情報保護法といった法的な課題も存在します。
正しい知識を持ち、自分に合った方法を選ぶことで、無駄なコストを抑えながら安心して手続きができます。「登録は自分で行う」という選択が、納得できるバイク購入につながるはずです。